私の職場には、変わった人がとにかく多い。
今回もその中の一人を、おもしろおかしくご紹介したいと思います
おかげさまで私自身は「変わった人に対応する能力」「処世術」「社会的知性」は、磨かれたように思います。
で、今回はこんな人です
「上司に残業を控えるよう注意されても、なぜか一人だけ超過残業を続ける人」
「担当作業をしないのに管理職のように振る舞い、会議に出たがりやたら発言したがる人」
「生産性は低いのに、残業だけは多い人」
…という、正直かなり扱いにくいタイプが存在します。私とは真逆ですな。
そもそも、私は残業しないで済むにはどうすれば?と普段から考えてます
また会議は必要最低限。伝達力・判断力・協調性のある人が少人数・短時間で行うべきだと思ってます。
【仕事】会議(ミーティング)に出るのをやめて、自分の時間を少し確保した話
現場の人間が直接会議であーだこーだ言うのでなく、言いたいことは上司に言うて話まとめといてよ!ってスタイルです。
そのために給料たくさんもらってるんでしょ?上司はうまく利用しましょう。
「会議はコンパクトに、決まった情報はダイナミックに共有せよ!」
で、話は戻って今回の方は部署と役職は私と同じで(※職歴は私の方が上なのですが)役職はついているけれど別に偉いわけではない。
日中の仕事は組立業務なのに、ほとんど現場で力を発揮せず“管理者ポジション”を気取り始めている。
但し自分が「これだ!」と思った仕事に対しては急にやりだしたりもします。
こういう人は、いったい何を考えているのでしょうか?
この記事では、世間一般の見方から心理学的な側面、そして実際の対策までまとめて解説します。
■ 世間ではどう評価されるタイプなのか?
まず率直に言うと、こうした行動をとる人は社会一般では次のように見られがちです。
● 「仕事しているフリの人」(いわゆる“フリーライダー”の一種)
日中は成果の見えない動きをし、残業時間だけで“働いている感”を出す。
● 「会議モンスター」
会議で発言する=組織への貢献と勘違いしているタイプ。
実務より会議を重視し、会議に出る自分に価値を見いだす。
● 「自己重要感にしがみつく人」
役職がある=偉い という誤解を持ち、実務能力より“存在感”で勝負しようとする。
● 「管理職のように振舞うだけの“偽管理者”」
ポジションに対して成果が伴わないため、周りからは逆に信用を失う。
名前を付けるなら、
「セルフ管理職タイプ」「マウント系プレイヤー」「働いている風アピール型」
といったところ。
■ この行動をとる人の心理(心理学的な背景)
こうした行動には、いくつかの心理的要因が絡んでいます。
① 自分の役割が曖昧なことへの不安
自信がない人ほど、
「自分は管理側の人間なんだ」
と周囲に示したくなり、行動が“上司モドキ”になる。
これは心理学でいう 自己防衛 の一種。
② 承認欲求が非常に強い
成果で評価されない代わりに、
・残業時間
・会議での発言
・管理職っぽい振る舞い
など 「目に見えやすい行動」で存在感をアピール しようとする。
③ 実務に自信がない(または能力不足)
実務で成果が出せない → 評価されない
↓
会議での発言や残業でカバーしようとする
↓
さらに周囲からの信頼を失う
という悪循環。
心理学ではこれを 代償行動(compensation) と呼びます。
④ “忙しくしている自分”が好き
やるべき作業を先延ばしにして残業に持ち込み、
「こんなに遅くまで働いている自分は偉い」
という自己満足を得るタイプ。
行動経済学では「サンクコストの誤謬」的思考がよく見られます。
⑤ 組織の序列に過剰にこだわる
役職=立場の強さ
と思い込み、
“役職者らしく振る舞わなければならない”
と自分を追い込む傾向も強い。
■ 周囲からすると面倒くさい理由
・実務をしない
・勝手に指示を出す
・会議で話を長引かせる
・生産性を下げる
・残業代だけ増える
…と、部署全体のパフォーマンスに悪影響を与えるため、
「ただの厄介者」に見えてしまいます。
■ では、どう対策すべきか?
● ① 役割と業務範囲を明確化する
“あなたは組立担当です”
と職務をはっきり言語化する。
曖昧なまま放置すると暴走します。
● ② 作業の成果を“見える化”する
・日ごとの作業量
・手順
・進捗
などを数値化 or 表形式にする。
成果が見えれば“管理職ごっこ”ができなくなります。
● ③ 会議の参加基準を決める
「この会議は実務担当者のみ参加」
「発言は議題に直接関係するものだけ」
などルールを作ると暴走が止まる。
● ④ 残業の承認制・理由書提出を徹底
「何をするための残業か」を提出させることで、
ムダ残業が激減します。
● ⑤ 直属上司が“役職の正しいあり方”を伝える
管理職とは
・生産性を上げる人
・現場を支える人
・責任を持つ人
であって、
“偉そうにする人”でも“会議に出たい人”でもないことを教育する必要があります。
● ⑥ メンタル的なケアも視野に入れる
こういう人は自己肯定感が低く、
「必要とされていたい」という思いが行動の裏にあることも。
完全に切り捨てるより、役割を与えつつ軌道修正する方が効果的な場合もあります。
■ まとめ:残業マンの心理は“承認欲求+自信のなさ”の複合体
今回のように
「日中は働かず、会議に出たがり、残業だけ多い」
というタイプの人は、
・承認欲求の強さ
・実務への自信のなさ
・管理職ゴッコで保とうとする自尊心
・曖昧な役割に対する不安
といった心理が複雑に絡み合った結果、
あの“面倒くさい行動”が生まれています。
組織としては、感情で対立するより
役割の明確化・成果の見える化・残業の管理
といった“仕組み”で正しい行動へ誘導する方が効果的です。
と、いうことで書いていたら面白くなってきたので次回は
会社としてはどう対応できるのか!?についてです
(続)”謎の管理職気取り” — 会社からの処分可能性を法律・労務観点で整理
お時間あれば続けてお楽しみください
では今回は以上です、ありがとうございました!




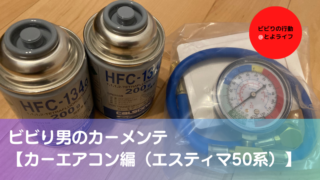
のJungle-Moc(ジャングルモック)を履いてみた感想-320x180.png)




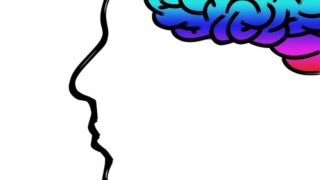

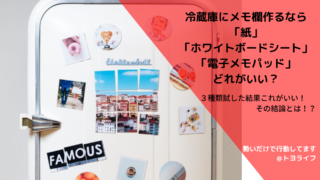



コメント